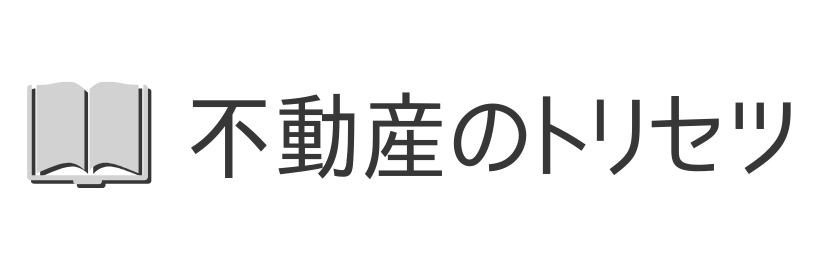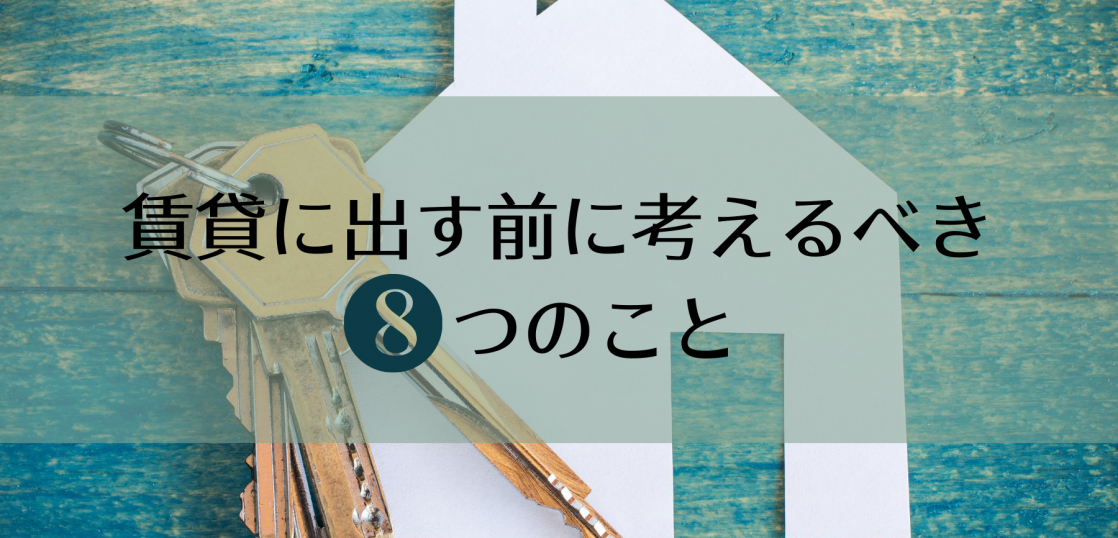2020年4月1日施行の改正民法や外国人労働者の増加等で、アパート・マンション経営をされるオーナーさまには、これまで以上に不動産に関する知識が求められるようになりました。
安心した賃貸経営をして頂くためには、賃貸に出す前に知っておくべきこと・注意すべきことがいくつかあります。
このブログでは貸し出す前にぜひ知っていいただきたいことをまとめましたので、これからの賃貸業にお役だていただけると嬉しいです。
それでは早速見ていきましょう!
目次
1.そもそも収益が上がるのか

不動産を賃貸に出す際には、まず周辺相場と比較した家賃設定をしたうえで「年間収入(家賃収入)」と「年間支出(ローンや固定資産税、修繕費等)」を計算し、収益化できるかを把握する必要があります。
将来的に不動産を売却することになると利回りが最重視されることから、売却時も見据えた家賃設定をすることも忘れてはいけません。
賃料を安くすることは賃貸業の最後の最後の手段です。
2、入居者像を明確に
賃貸経営をしていくうえで、エリアに合わせたターゲット層へのアプローチをすることはとても重要なことです。
そのためには、入居者像を明確にすることが非常に大切です。
入居者像が明確になると…
- 部屋の内装をターゲットに絞ったものに仕上げられ、周辺物件と差別化が図れます。
- より的確でターゲットを絞った条件で募集することで、入居者が見つかりやすくなります。
どんな商品でも”ターゲット(ときにペルソナと呼ばれます)”を考えることは非常に大事なことですので、お部屋を貸し出すときも同じです。
イーエムラボでは同マンションにどんな人(年齢、職業、単身かファミリーか等)が住んでいるかをオーナーに教えてもらい、ターゲットに合ったリスティングをしています。
3、募集条件について

常々、オーナー様より敷金や礼金の募集時の金額設定について次のようなご相談をうけます。
「敷金」は、何ヶ月分がよいか?
敷金は一般的には1ヶ月分となっていますが、必ずしも1か月分でなければいけないという決まりはありません。
例えば、ペット可の物件では、退去時の原状回復工事代が高くなるリスクを補うため、2ヶ月~3ヶ月分をお預かりする傾向があります。
イーエムラボではそのうち、1ヶ月分を償却とさせてもらい、原状回復工事代に充てる内容の契約にしています。
自主管理の場合はオーナー自身で預かってもらい、管理物件に関しては管理会社側で預かるケースもあります。
「礼金」は、何ヶ月分?
礼金についても1ヶ月分が一般的ですが、最近は、「礼金ゼロ」の物件を求めるお客さまが多い傾向にあり、実際に「礼金ゼロ」の物件が増えてきました。
礼金をゼロにすることは、オーナーさまにとっても空室が続くリスクを少しでも回避するためでもあるので、周辺の募集状況もチェックしながら、設定してください。
4、物件の管理について
賃貸物件の管理方法は、管理会社によって違いがあります。
賃貸物件の管理は、大きく分ければ、オーナーさまご自身で管理していただく「自主管理」と、管理を一任する「管理委託」に分かれます。
しかし、「清掃や補修の手配はどうする?」「税金や管理費、修繕金の建て替えまでやってくれる?」などは、管理会社やプランごとに異なるので注意しましょう。
自分がどこまでやるか、管理委託費としてどれくらいの費用を支払い、どの程度の管理業務をしてくれるのか等、細かいところまで管理会社の担当者と話し合われることをおすすめします。
個人的には、管理業務はプロにお任せするのがよいのではないかと思います。
入居者さんからは日頃から「○○が動かない」「変な音がするので見に来てほしい」など、連絡があるケースがあるので、すぐに対応してくれる不動産会社に管理を委託しておくと安心かと思います。
5、設備不具合による修繕費用は誰の負担になるのか?
修理や修繕にかかる費用のご負担は、基本的にオーナー様です。
(入居者が故意に壊した場合は、入居者負担になります)
室内における設備の使用料は毎月の家賃に含まれていますので、「給湯器が壊れてお湯が出ない」「エアコンから風が出てこない」等の不具合が発生した場合の修繕費用は、オーナー様の負担となります。
(※残置物の場合は直す必要がありません。)
設備の不具合が発生した際は、迅速な対応が必要です。
すぐに修繕できなくても、修繕に伺える日時等を早めに入居者さんへ伝える事が、入居者満足度向上にも繋がります。
特に夏場のエアコン故障は家賃を下げてくれ!故障した期間の家賃をどうにかしてほしい等のトラブルにもなりかねないので、迅速な対応が必要になります。
6、「定期借家契約」と「普通借家契約」の違い

「定期借家契約」の特徴
契約期間が終了した時点で、契約が終了する契約です。賃借人様とオーナー様の間で合意があれば再契約も可能ですが、基本的には更新のない契約となります。
「普通借家契約」の特徴
「賃貸」といえば、こちらの「普通借家契約」が一般的です。オーナー様からの解約は、正当な事由がない限りできません。
普通借家契約では一度賃貸すると、よほどの事情がない限り、オーナー様からの解約ができません。
そのため、不動産を賃貸に出すオーナー様は、まず「ご自身で利用されることはないか」「売却する予定はないか」ということを考えてから、普通借家契約にするのか定期借家契約にするのか判断するようにしてください。
実需(マイホームとして購入する人)の需要がありそうな物件で、将来的に手放すことを考えている場合は、定期借家5年などで貸し出すのが無難なように思います。
「定期借家契約」と「普通借家契約」の違いについは、こちらのページでも解説しております。
定期借家は普通借家よりも期限があるということで敬遠する人もいるので、賃料を若干さげたり、期間の延ばして更新料が不要であることをアピールしたり、工夫することが重要です。
7、安定した賃貸経営をするための家賃保証会社
家賃保証会社は、大きく分けて次の2つのタイプに分かれます。
代位弁済型
家賃滞納が発生した時点で、オーナー様が必要書類を記入して保証会社へFAXにて滞納を報告しなければいけません。滞納報告を受けた保証会社は、オーナー様の指定口座へ家賃の立替払いを行うと同時に、入居者様へ督促を行います。
集金代行を兼ねた立替支払型
入居者様の指定口座から毎月決まった日に家賃が引き落とされ、オーナー様の指定口座へ家賃が振替えられます。万が一家賃の引き落としができなかった場合、保証会社は自動的に家賃の立替払いを実行し、入居者様へ督促を行います。
2つのタイプの大きな違いは、家賃滞納発生時の対応です。
より確実で安定した賃貸経営をしていただくためには、②集金代行を兼ねた立替支払型の保証会社をおすすめいたします。
また、管理をお願いする不動産会社には予め、どのタイプの「保証会社と契約しているか」を確認しておくといいでしょう。
オーナーさま自身で保証会社と契約することは原則できませんので、不動産会社に依頼するまえに保証会社についてはご質問することをオススメします。
イーエムラボでは全ての保証会社で立替支払型を選択しています。
多言語で対応可能な保証会社、原状回復費や退去時の保証が厚いところ、学生向けは保証料が安いところ等、物件やお客さまによって選べるように複数の保証会社と契約しています。
8、原状回復費用の負担割合

原状回復とは、入居者が借りた当時の状態に戻すということではありません。
なかには、クロスの張り替えも全額借主負担だと思っている大家さんもいらっしゃるのですが、設備には「耐用年数」が考慮されるので、全額を借主に払ってもらうことにはなりません。
退去時の室内状態が通常使用による損耗
⇒オーナー様負担となります。
※経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は賃料に含まれるという考え方です。
明らかに通常の使用を超えることによる損耗
⇒入居者様負担となります。
※案件にもよりますが入居者負担となる原状回復でも耐用年数が考慮されますので、修繕費全額を入居者様へ請求という事は難しい場合がほとんどです。
上記のような原状回復についての考え方は、国土交通省が定めたガイドラインや、2020年4月1日施行の改正民法でも明文化されています。
賃貸借契約を結ぶときには”賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書”という書類でどちらがどんな場合に費用を負担するのか?というのがまとめられているので、その内容に基づき、オーナー様、入居者様が費用負担することになります。
まとめ:賃貸に出す前には管理プランや内容の確認を
これからご所有物件を賃貸に出すことをお考えの方は、ぜひ今回お伝えした8つのことに留意して、トラブルのない賃貸業を目指してください。
安心かつ収益が最大化するための賃貸経営のためには、オーナー様が知っておくべきことをしっかり認識すること、そしてご自身にあった管理プランの選択することが重要です。
入居者の方には快適にお住まいいただき、オーナーさまには長期的に「純資産」を増やしていってほしいと願っています。
分からないことがありましたら、お気軽にご相談ください。