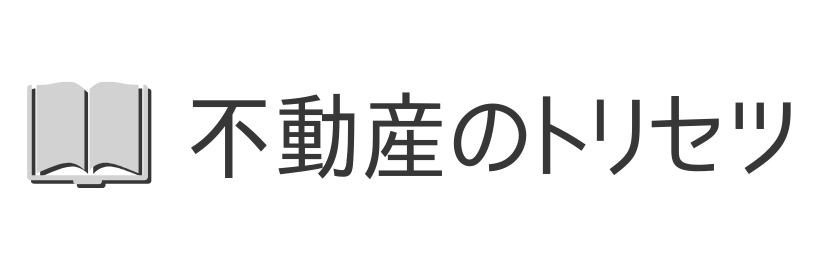アパートや賃貸マンションを経営する不動産オーナー様にとって、滞納がなく毎月安定した家賃収入が入ることは、一番重要なことですよね。
特に、アパートローンを利用されている場合は、家賃滞納のリスクは切実な問題です。
では、実際に家賃の滞納はどれくらいあるのでしょうか?
(公財)日本賃貸住宅管理協会の賃貸住宅景況調査によると、2022年度上半期における全国の月末での1ヶ月滞納率は0.8%(首都圏は0.4%と低いものの、関西圏 とその他エリアは3.3%と2.3%)また、全国の2ヶ月以上滞納率は0.3%程度です。
以前に比べて低率になっているのは、保証会社による代位弁済が浸透しているからだと思われます。
参照元:(公財)日本賃貸住宅管理協会「日管協短観(2022年度上期)」
そこで今回は、家賃滞納のリスクを減らす上で有効な保証会社の保証について取り上げます。
目次
賃貸契約で増えている保証会社とは?
保証会社は、もともとは借主(入居者)の連帯保証人を代行することを目的としたサービス会社です。
借主(入居者)が、保証会社に一定の保証料を支払うことで、滞納が発生した場合に連帯保証人を代行して、家賃を肩代わりするサービスです。
2008年のリーマンショック以降、連帯保証人を立てられない借主(入居者)の増加と共に、保証会社を使うケースが増えてきました。
そして近年は、市場の拡大とともに連帯保証人がいる場合でも保証会社を使うケースは増えており、サービス内容もより充実しています。
このような経緯から、保証会社には「連帯保証人代行」としての役割が大きいため、保証料は貸主(オーナー)ではなく借主(入居者)が払うことが一般的です。
入居率を上げるために、初回の保証料のみ貸主(オーナー)が負担するケースもありますが、保証会社に入ってもらうメリットは大きいと言えます。
個人的には、たとえオーナー自身で払ってでも、加入してもらうのをオススメしています。
以前、オーナーチェンジ物件を購入した方がどうしても保証会社を付けたいということで、借主ではなく、ご自身で保証料を支払、保証会社に加入したオーナー様がおられました。
※借主さんの申込みになるため、借主さんの承諾が必要になります。
保証会社のメリットとは?
保証会社の大きなメリットは、家賃滞納時に発生する様々なリスクを軽減できる点です。
保証会社を使わない場合には、滞納された家賃を回収するために、催促のための法的な手続きが必要になります。
手続きを弁護士に依頼すると、場合によっては、滞納されている家賃を上回る費用がかかることもあります。
何とか家賃を回収できたとしても、赤字になってしまい、アパートローンの返済計画に悪影響を与えかねません。
保証会社に加入することで、こうした滞納による様々なリスクを軽減できます。
なぜなら保証会社から、滞納した家賃を立替えてもらうだけでなく、契約弁護士による督促状の発行など、法的な手続きの多くを代行するサービスをまるっと受けられます。
保証会社の種類
滞納が発生した時に受けられるサービスは、保証会社によって異なります。
保証会社は、大別すると「滞納報告方式」と「集金代行方式」の2種類で、それぞれメリットとデメリットがあります。
1.滞納報告方式
滞納が発生した場合、貸主(オーナー)が必要書類を記入して保証会社に報告する方式です。
報告を受けた保証会社は、家賃を貸主(オーナー)に建替え払いを行うと同時に、立替えた家賃を借主(入居者)に督促して回収します。
この方式のメリットは、通常の保証料以外に手数料がかからないため、コストが安い点です。
デメリットは、貸主(オーナー)は、滞納の発生ごとに保証会社に書面での連絡が必要な点です。そのため、立替えた家賃が入金されるまでタイムラグが発生します。
また、保証会社への連絡が遅れると、免責となり家賃を立替えてもらえない場合もあります。
2.集金代行方式
保証会社が、貸主(オーナー)や仲介会社の代わりに、借主(入居者)から家賃の集金代行を行う方式です。
滞納が発生した場合は、保証会社が家賃を貸主(オーナー)に建替え払いを行うと同時に、立替えた家賃を借主(入居者)に督促して回収します。
この方式のメリットは、保証会社が借主(入居者)との間に入って家賃の集金を行うため、滞納が発生しても連絡が不要で、入金までのタイムラグが発生しない点です。
しかしその反面、通常の保証料以外に手数料が発生したり、コストが若干高くなるデメリットがあります。
ちなみに、イーエムラボでは2.の集金代行方式の複数の賃貸保証会社と契約しています。
弊社では、学生・外国籍・法人それぞれにあった保証契約をご提案しています。
保証会社はオーナーが選べるの?
大きくわけて2種類ある保証会社ですが、選ぶことは出来るのでしょうか?
保証会社は、基本的には仲介会社が取り扱っている会社と契約することになるので、オーナーが自由に選べないのが実情です。
しかし、一社ではなく複数の保証会社と提携している仲介会社に、募集を依頼することで選択肢が増えます。
保証会社の選択肢が多いことは、貸主(オーナー)と借主(入居者)の両方にメリットがあります。
なぜなら、保証会社には、「滞納報告方式」と「集金代行方式」の種類分け以外にも、
外国人に強い
学生でも通りやすい
保証料が安い
など、それぞれ強みがあるからです。
保証会社と契約するためには、「入居者の審査」を通る必要があります。
その審査によって、入居者の収入などの条件から滞納のリスクが精査されます。
この時、滞納のリスクが高いと判断されると、最悪の場合、「審査落ち」となり、家賃保証を受けられない場合もあります。
*落ちた場合「なぜ、落ちたのか」については一切答えてもらえません。
また、「審査落ち」という結果になると、入居を断らざる得なくなって空室期間が延びるので、オーナーと入居者の双方にとって大きな損失となります。
なぜなら、空室期間が延びればその間は家賃が入らないので、賃貸経営に悪影響を及ぼしかねません。
同時に、審査に落ちた方は、また一から次の物件を探さなければなりません。
そこで、「学生」や「外国人」など、借主の条件に合った強みを持つ保証会社を選ぶことが大切です。
そうすることで、保証料を低く抑えられると同時に、審査落ちのリスクを軽減することができます。
保証会社の契約書を事前に確認しましょう
保証会社選びで、もう1つ忘れてはならない大切なことがあります。
それは、実際に滞納トラブルが発生する前に、契約内容を理解しておくことです。
契約内容をよく知らずに、トラブルが発生してから「保証対象外で家賃を回収できない」となれば、アパートローンの返済計画にも悪影響を与えかねません。
そこで、
- 滞納報告方式の場合、免責となる報告の期限はいつまでか?
- 滞納が続いた場合、何ヶ月まで家賃を保証してくれるのか?
- 督促状の発行など、法的な手続きをどこまで代行してくれるか?
など、契約内容を理解した上で、物件に合った保証会社を選ぶことが大事です。
まとめ
今回は、保証会社について取り上げました。
保証会社選びは、滞納のリスクを減らしてアパートローンの返済をスムーズに進める上で、とても大切です。
保証会社を選ぶ上で、重要なポイントは2つです。
1つ目は、入居者に合わせた保証会社選び。
様々な入居者の条件に合わせるためには、多くの保証会社と契約している不動産会社を選ぶことが、望ましいでしょう。
2つ目は、契約内容の確認。
いざ滞納トラブルが発生した時に「保証対象外だった」ということがないように、事前に契約内容をしっかりと確認しましょう。
以上の重要な2つのポイントを、しっかりとおさえて滞納のリスクを減らし、安定経営を続けてください。
物件を貸し出す上でご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。